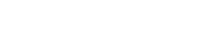離婚の際に活用できる年金分割制度

離婚の際に必ず直面する財産分与。
そんなとき活用できる年金分割という制度をご存知ですか?
「ずっと専業主婦だったので、離婚した後の生活が心配!」
そんな方にはぜひ知っておいて頂きたい制度です。
では、年金分割の制度がどんな時に利用できるか、実際にどのような手続なのかをご案内します。
そもそも年金分割とはどんな制度?
離婚等の場合に、当事者の請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者で分割する制度です。
従来の制度では、婚姻期間中に夫がサラリーマンで厚生年金に加入、妻が専業主婦という場合、夫は厚生年金部分についても年金を受け取ることができるのに、妻は基礎年金部分しか受け取れませんでした。
専業主婦の妻の家事分担などの協力があってこそ夫が保険料を払い続けることができたとも考えられます。そこで、妻にもこの期間の保険料による年金について公平に受け取ることができるように認められたのが年金分割の制度です。
このような制度ですから、ご自身の年金の少ない方が、多い方に対して分割請求することになります。

年金分割における注意点
①夫が受け取ることになる年金の2分の1をもらえるという制度ではありません。
年金分割の対象となるのは、厚生年金・旧共済年金に限られます。
国民年金(基礎年金)部分については、分割の対象とはなりません。
②分割するのは年金自体ではなく、年金の記録です。
具体的にいくらの年金を受け取ることができるのかは、年金保険料を納めてきた記録に基づいて計算されます。
年金分割はこの年金の納付記録を分割するものです。
◎受給開始年齢に達しないと支給されない
ご自身が受給開始年齢に達していないと受給できません。
◎年金加入期間には算定されない
年金分割によって分割を受けた者が年金の加入期間を満たさない場合には年金を受け取ることはできません。
加入期間を満たさない場合は、そもそも年金を受け取ることができないので、年金分割のメリットを受けることができないのです。
※年金加入期間は従来25年とされていましたが、平成29年8月に改正法が施行され10年となりました。
加入期間が10年以上25年未満の方も、平成29年9月分から受給が可能になり、10月から支給が始まります。
◎分割した側の夫が死亡した後も年金を受け取れる
分割した側の夫が死亡した後も、分割を受けた妻は、分割した記録によって計算された年金を受け取ることができます。
③分割請求の期限は、原則として離婚したとき、婚姻の取消をしたとき等の翌日から2年以内です。
年金分割における分割請求には期限があるので、離婚することが決まったら忘れずに手続をしましょう。
年金分割の種類
①合意分割制度
当事者双方の合意あるいは裁判手続により按分割合を定めることにより、その割合で年金を受け取ることができます。
分割の対象は婚姻期間、制度の始まった平成19年4月以前の期間も対象となります。
分割の割合は合意で決まります(最大2分の1)。
②3号分割制度
国民年金の3号被保険者(専業主婦など)が、夫の厚生年金記録の2分の1を分割することができる制度です。
分割の期間は平成20年4月以降の3号被保険者期間
分割の割合は2分の1。
年金分割の手続
①3号分割制度
合意は不要。
年金事務所等年金手続を取扱う役所・機関に元夫婦の戸籍謄本とともに「年金分割の標準報酬改定請求書」を提出して、分割を請求するだけでよいです。
②合意分割
a 合意するため(按分の割合を出すため)の前提に年金に関する情報を取得する
- 年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を入手
- 必要事項を記載、年金手帳、戸籍謄本または住民票とともに提出
b 按分割合の協議
按分の割合は最大で2分の1ですが、多くの裁判例は2分の1と判断しています。
c 当事者で協議がまとまらない場合には、離婚調停・離婚審判・離婚裁判で決定する。
d 年金分割の改定請求を年金事務所にする
- 按分割合が協議でまとまった場合
→2人で合意書、年金手帳、元夫婦の戸籍謄本とともに「年金分割の改定請求書」を提出する
ただし、合意書を公正証書にしておけば一方だけで手続ができます。 - 離婚調停・離婚審判・離婚裁判による場合
→分割割合を定めた調停調書・判決の謄本または抄本等を年金手帳、元夫婦の戸籍謄本とともに提出する。
弁護士は「財産分与に有利な方法を知っておけばよかったのにと後悔すること」を防ぐ心強い味方です
年金分割という制度があるにも関わらず、それを知っている方が少ないのが現状です。
「知っていればよかったのに」という後悔を防ぎ、最善の財産分与のために弁護士が力になります。
一人で戦うよりもずっと心強い味方になります。
離婚問題で夫婦間の話し合いがまとまらないなど、お困りの際は福島県いわき市の佐藤法律事務所へご相談ください。